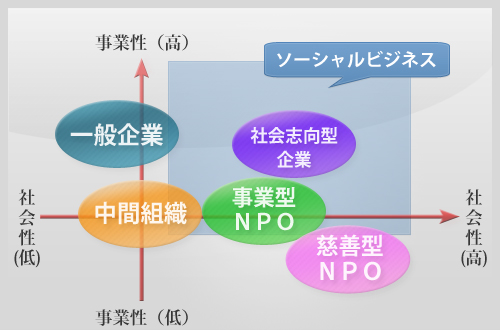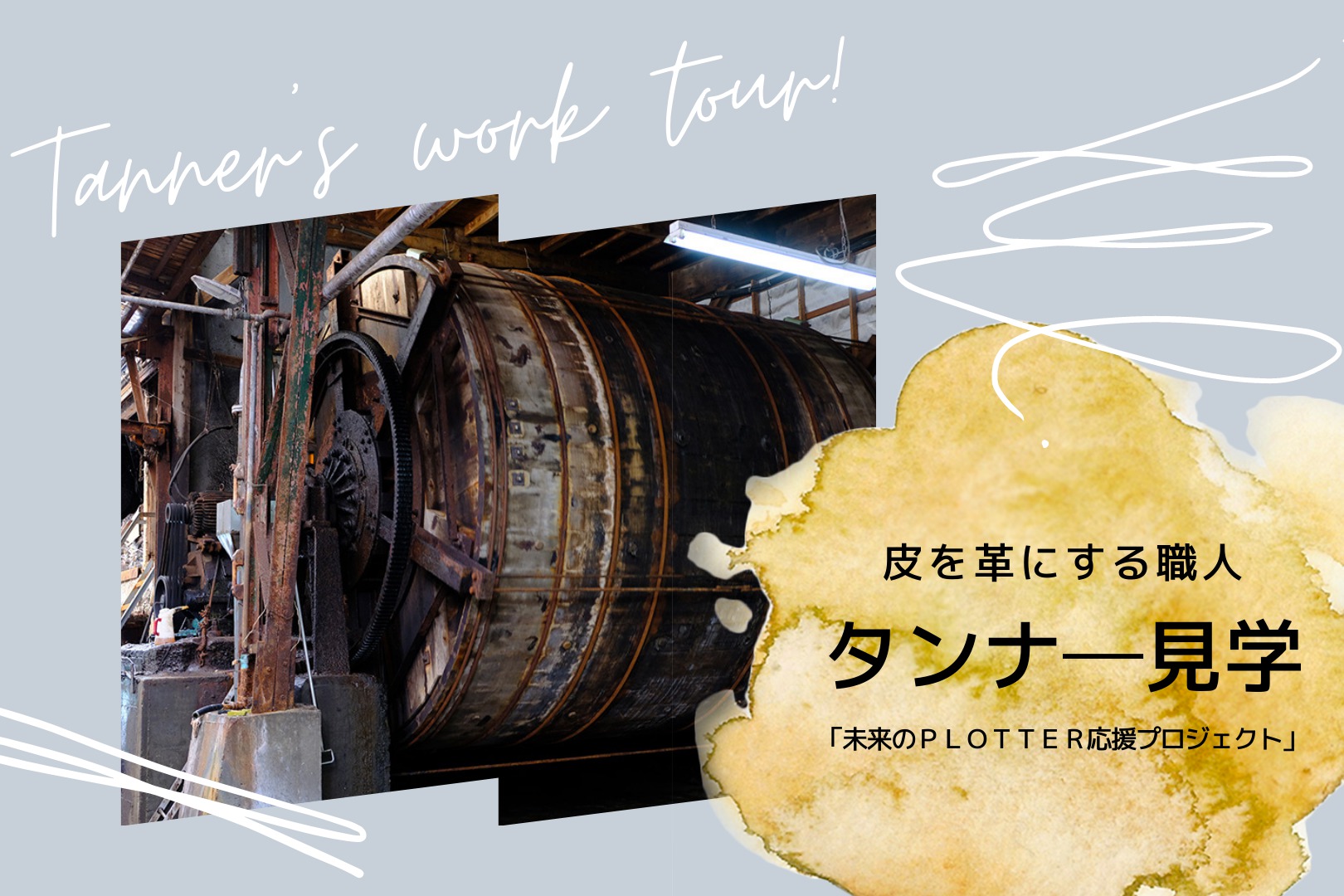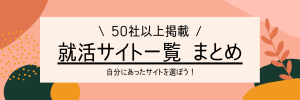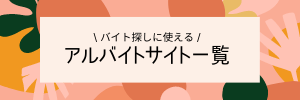今回インタビューさせていただいたのは、森合音さん。
森さんは過去にご自身がアートの持つ癒しの力に救われた経験から、心身の「痛み」を抱えた患者さんがやってくる”病院”という場所にアートを導入し、その空間に安らぎと安心感を芽吹かせるホスピタルアートの取り組みに長年携わっていらっしゃいます。
アートディレクターとしてどのような思いを胸にこの活動を続けてきたのか。またコロナ禍で変わりゆく医療現場に何を思ったのか。その心中を取材させていただきました。
NPO法人アーツプロジェクト理事長
1972年徳島県生まれ。大阪芸術大学写真学科卒業。30歳の時、突然の心筋梗塞で最愛の夫を亡くす。夫の遺したカメラで2人の娘の日常を撮った写真集「太陽とかべとかげ」で、2005年富士フォトサロン新人賞を受賞。辛い時にはカメラを手に風景を写真に収めるという行動を繰り返す中で、アートがいつしかセルフカウンセリングの手段、辛い気持ちを吐き出し和らげる存在として自分に寄り添ってくれていたことを実感。アートの持つ「心の傷を癒す力」を体感し、2008年より香川小児病院(現・四国こどもとおとなの医療センター)でホスピタルアートに携わる。
目次
キーワードは、痛みに寄り添う「対話」
ー「ホスピタルアートディレクター」として、具体的にどのようなお仕事をされているのでしょうか。
「四国こどもと大人の医療センター」にアートディレクターとして常駐し、院内に取り入れるホスピタルアートの企画・実践を行っています。それとは別に、NPOのアーツプロジェクトという団体でこうしたホスピタルアートの取り組みを色々な病院に広げていく活動も行っております。医療現場にアートを届けたいと要望のあった病院に出向き、前述の病院で実践してきたことをベースとしてアートの提案やアドバイスをさせていただきながら、その病院にふさわしいアートの形を現場の方々と共に見出していくという活動です。
ーアートが病院に導入されるまでの流れをお伺いしたいです。
院内で生じた問題を受け、「アート」が出動するという流れになっています。例えば12年前、精神科病棟の殺風景な空間をどうにかできないだろうかという相談が持ち上がったことがあります。そうした「痛みの問題」一つ一つと向き合い、”ヒアリング”をベースにしてアートの企画を進めていくのです。

初めから私一人でどういうアートにするか細かく決めたりディレクションしたりということはしません。私の頭の中のイメージはむしろ常に空っぽと言ってもいいかもしれないです。大切なのは現場の方々の声を丁寧に拾い、そして何よりそこに入院されている患者さんの気持ちにどこまで寄り添えるか、というところ。だからこそ私は「対話」というものをとても大事にしています。
「アンケート」だと、こちらサイドで枠を作った中でのものになってしまいますから、どうしても拾える内容が限定されてしまいます。その点「対話」というのは、どういった問いを投げかけられるのかによって答えがその都度変わっていく。その不確定な感じがアートを生み出していく上でとても大切だと思っています。
―確かに今もこうして私が投げかける問いによってこの対話の方向性や中身はいかようにも変わっていく可能性を感じます。この「余白的な感覚」を大切にされているのですね。
そうですね。特に「医療」というのは、科学的なエビデンスや検査データを重要視しますから論理的な側面を強く持ったものであると言えます。もちろんその科学性は、批判するべきものではないし必要なものです。ただ人間はそれだけで生きているのではなく、個々の主観や体験によって、意識や選択、運命さえも変わっていきます。命と向き合う医療現場の中でそういった余白の部分をアートによって担保しておきたい、という気持ちはありますね。
ー患者様と「対話」をする中で生まれたアートのうち、印象的だったものを教えていただきたいです。
院内19ヶ所の壁に、3つで1セットの凹みをあえて作った“ニッチ”という飾り棚があるのですが、これはまさに患者さんと対話する中で生まれた当院の象徴的なアートです。

ここは、入院患者さんやボランティアスタッフの方々が作った匿名のプレゼントをメッセージカードとともに忍ばせておくスペースで、その扉を開いた人であれば誰でも置いてあるプレゼントを持ち帰ることができるというシステムになっています。この仕組みの原点となったのが12年前に入院していたある女の子との「対話」でした。
その子は「これを手術を怖がっている子供たちに渡して、手術後も持って帰ることができるようにしてあげて欲しい」と、ある時たくさんのぬいぐるみを作って私に渡してきたことがありました。その子の言葉通り私がぬいぐるみを手術前の子供たちに渡すと、みんなとても喜んで、患者さんもオペ担当の方もありがとうと感謝の言葉を口にされたんですね。私はその感謝の声を私ではなく作った本人に直接届けたいと思い、「患者さんに直接渡してみるのはどうかな」と提案してみたのですが、その子は「それはいいんです」と。
どうしてだろうと疑問に思って話を聞いていくと、「もし私の顔を患者さんやオペ担当の方が知ってしまったら、会うたび私たちには「ありがとう」と”言う義務”と”言われる義務”が生まれてしまう。それは常に作り続けなければというプレッシャーにもなるし、体調によってしんどい時には作ることをお休みしたくなることもあるかもしれない。だから匿名でやっていきたいんです。」と言ったのです。
贈る方も貰う方も匿名で気楽で嬉しい。そうしてこの小さな扉が、院内で「心の交流」という新たなコミュニケーションの場として機能していく。これはとてもいい連鎖だなと思い新病院開設時に改良して取り入れたのが、今のこの“ニッチ”になります。

どのホスピタルアートプロジェクトも根底にある原理は同じです。お互いに負担のないポイントを探しながら誰かが誰かを思う気持ちを形にしていくということ。それが私の役目だと思っていますし、そのためにはやはり「対話」が必要不可欠であると日々実感しています。
変わりゆくコロナ禍の医療現場。アートで分断を超えていく
ーこのコロナ禍で、普段ホスピタルアートの活動に携わっているボランティアスタッフの方々の活動にもやはり制限は生まれてしまったのでしょうか。
今までは毎週のように演奏会や紙芝居といったイベントが行われ、ボランティアさんがそこで入院患者さんと可能な限りコミュニケーションを取っていました。ところがコロナ禍以降、もちろんそうした活動が一切出来なくなってしまったんですね。ですが先程のニッチに入れるプレゼントとメッセージカードを皆さん作り溜めてたくさん送って下さったり、コロナ禍であってもやり方を工夫しながら関わって下さっています。
当院アートチームとしても、新たに「院内テレビ局」というものを立ち上げました。そこで、ボランティアの方々がリモートで行うイベントの様子を流したり、近くの大学の学生さんと連携して演劇調の病院紹介動画を作ったりと、アートは医療にとって大切だと考える人達と協力して試行錯誤しながら進めています。

ー院内外をつなぐ新たなコミュニケーションの形を模索されているのですね。コロナという”共通の「痛み」”にアートが優しく寄り添っているような感じがします。
冒頭でお話したように、私たちは問題解決と創造性をセットにして痛みを希望に変えるためにアートを病院に導入してきました。暗い壁を明るくしたい、荒れてしまった芝生を何とかしたい。これまではそうした現場の個別の痛みに一つ一つ「点」で答えていくというアートの仕事だったのが、コロナ禍以降はまだ先の見えない医療現場全体に対するアクションになってきたので、より「面」で関わっていくようになったなという実感はありますね。
ーこのコロナ禍でクローズアップされるようになったのが日々ひたむきに命と向き合う医療従事者の方々の激務の日々です。ケアする側の方々に対してもアートによる癒しのアプローチというのは可能なのでしょうか。
医療提供というのはとても大変なお仕事です。だからこそ常に患者さんの様々な「痛み」に向き合う医療職の方々もまた、自分自身の「痛み」や辛いという気持ちを、癒したり言葉にして発したりすることのできる環境が医療現場にとって大切だと考えています。そのための場所として当院には、「メディテーションルーム」と「ボランティア室」という二つの部屋が存在します。

右:メディテーションルーム
「メディテーションルーム」は一人静かに好きな音楽を聴きながら、ゆっくりと心身をリセットをする場所。そして「ボランティア室」は相談事を気軽に話せる場所。痛みを癒す場所と痛みを表現する場所として両者はケアする人のケアをそれぞれに担っています。
心の自然治癒力を高めるアート。その力を信じて
ー最後に今後の展望、これから先の活動に込める思いをお伺いしたいです。
アートには心の痛みを表現させてくれたり、受け止めてくれたり、しかもそれを希望に変えてくれるという心の自浄作用、自然治癒力を高める力が確かにあります。
これからもアートの持つその力を信じて院内外の様々な人達と関わり合い、そこにぜひ若い世代の方も加わっていただきながら対話をし、まだ見たことのないものを共に立ち上げていけたらと思っています。
ー素敵な活動を取材させていただきありがとうございました!
アートに感じる安らぎとぬくもり。きっと病院という独特の空間の中で生じる、手術前の不安や検査前の緊張感、入院中の寂しさといった様々な心の揺らぎの一つ一つをもアートは柔らかく優しく包みこんでいるのだと思います。
四国こどもとおとなの医療センターでは、本記事で紹介した場所以外にもたくさんのアートが導入されています。どのアートも痛みに寄り添う暖かさに満ちたとても素敵なものです。ぜひ下記リンクよりご覧ください。
HP:https://shikoku-mc.hosp.go.jp/about/hospitalart.html