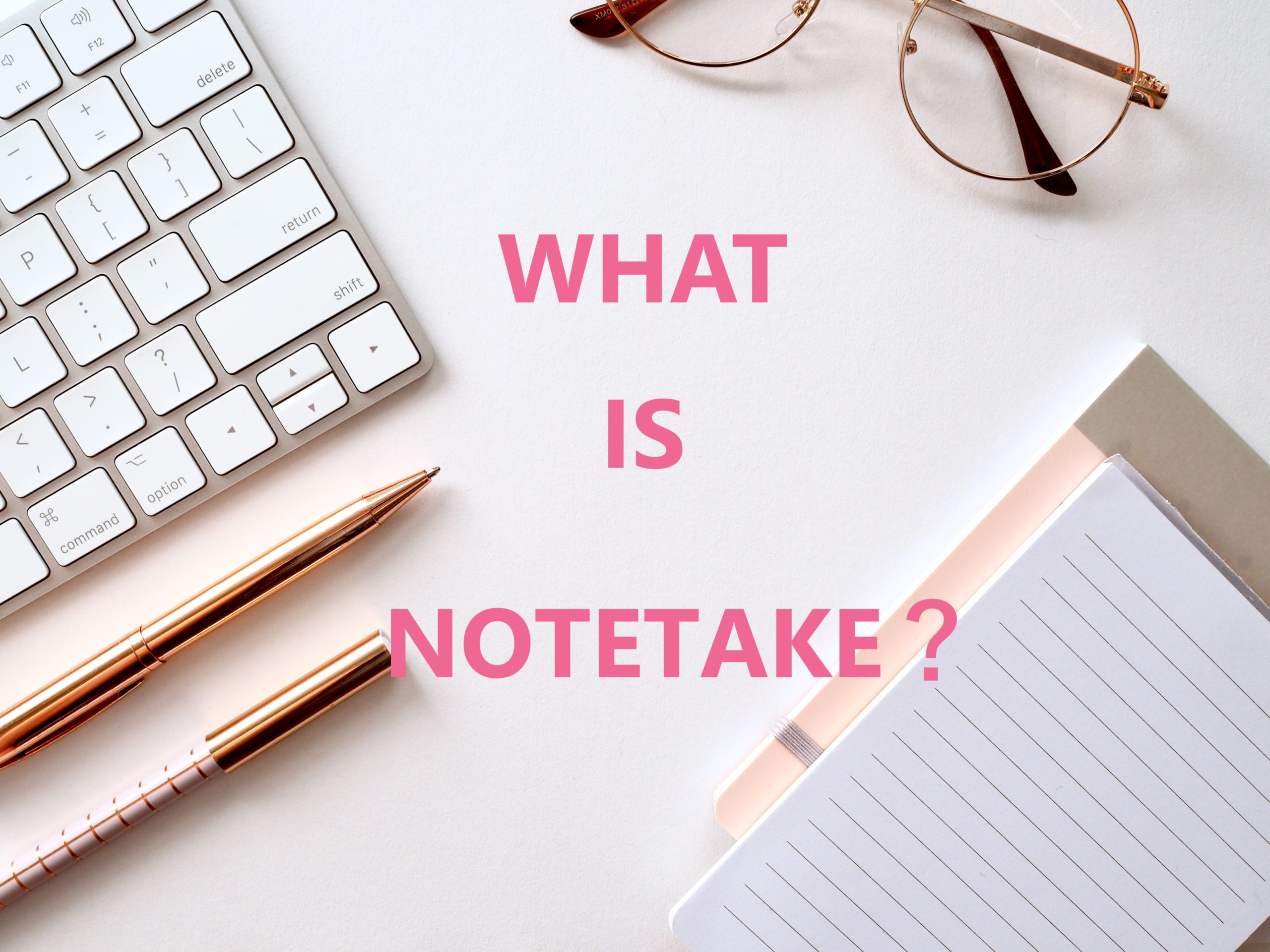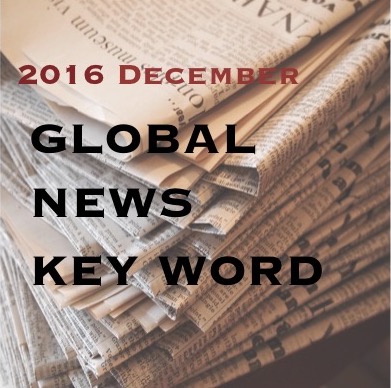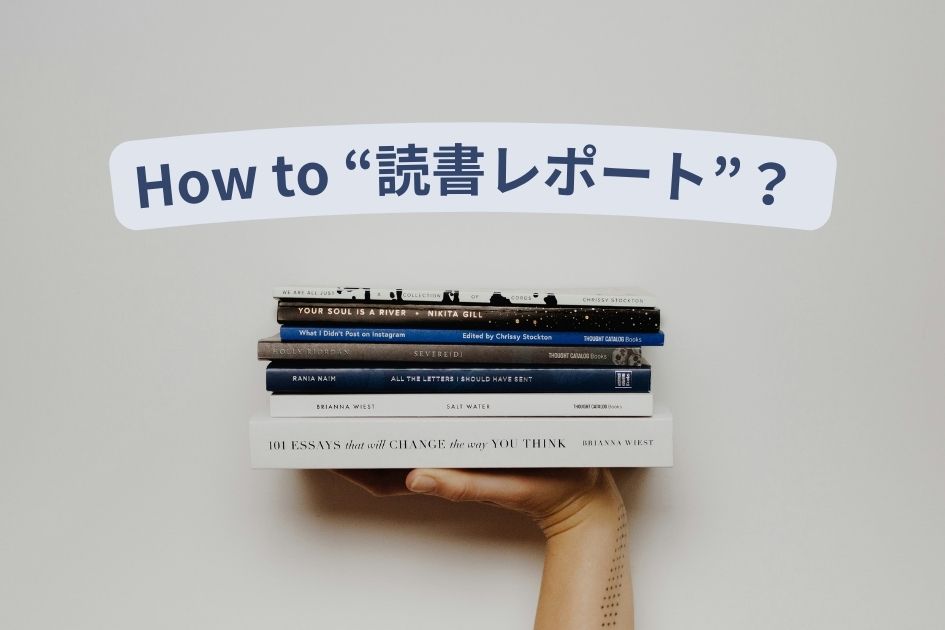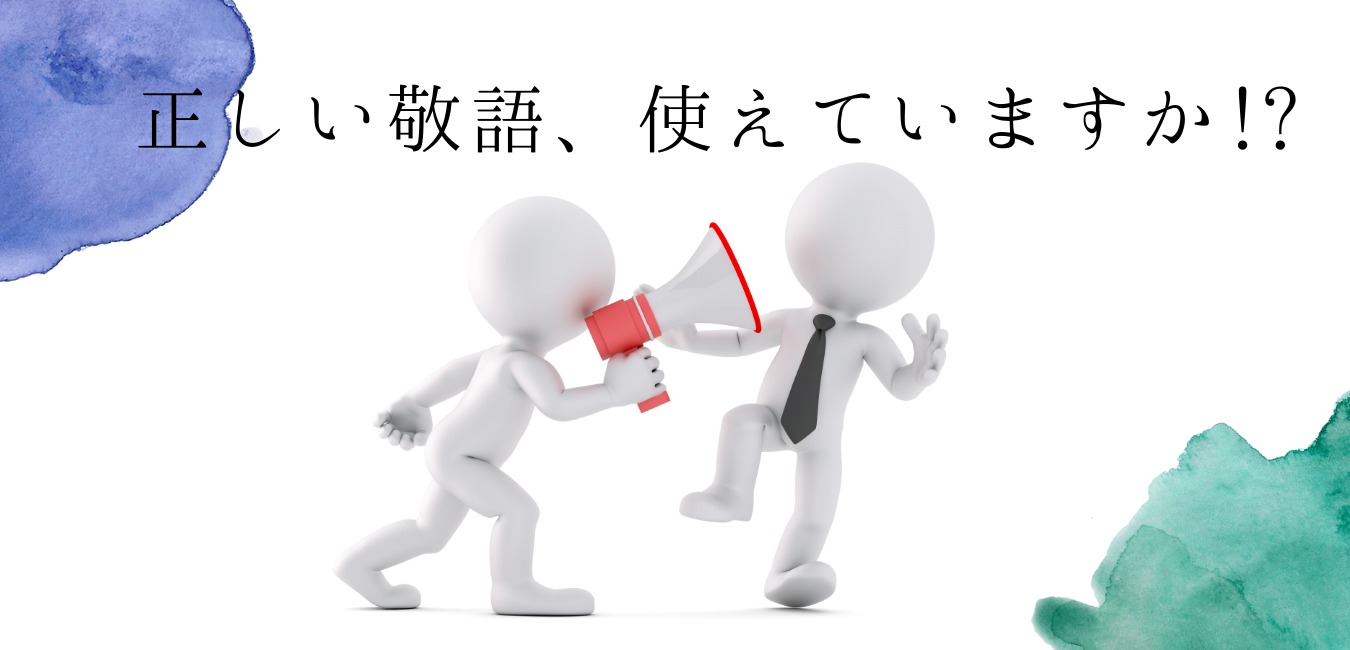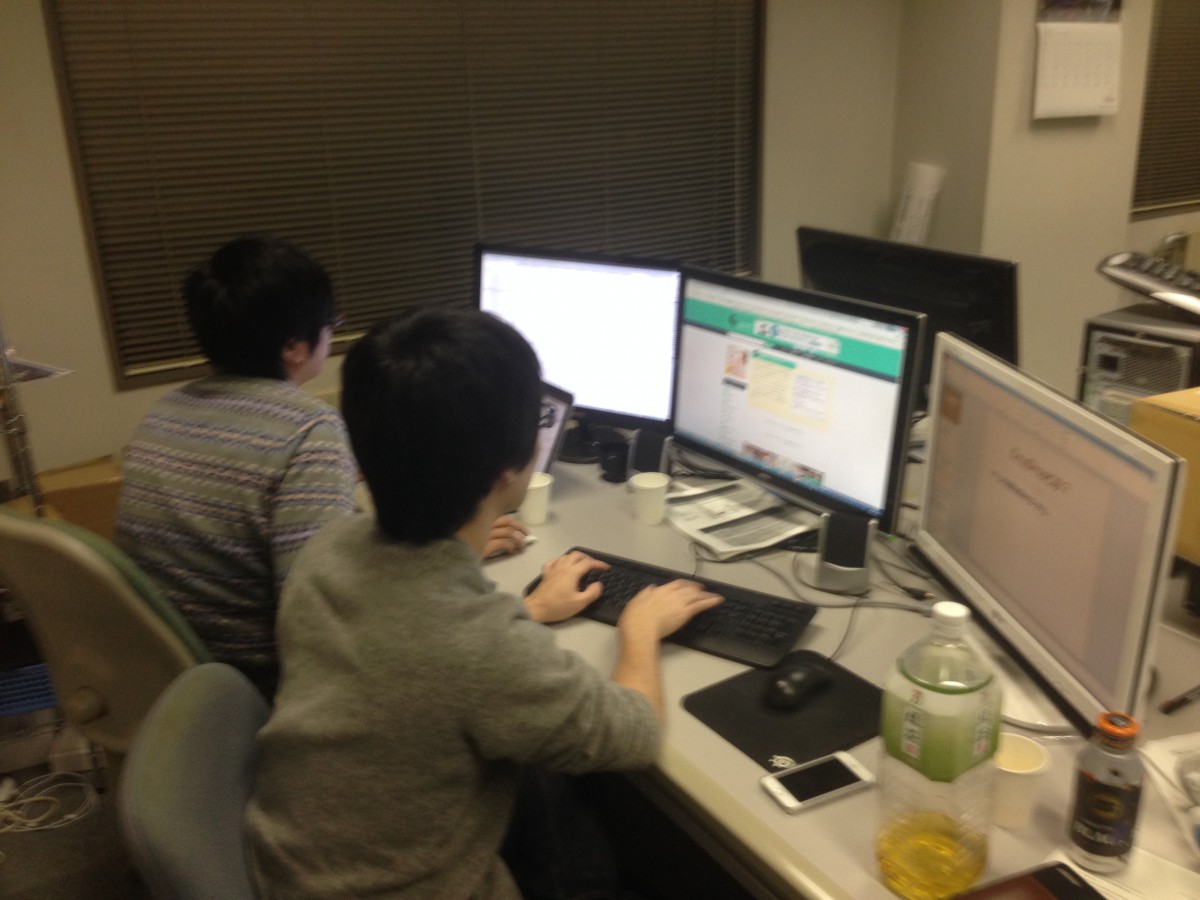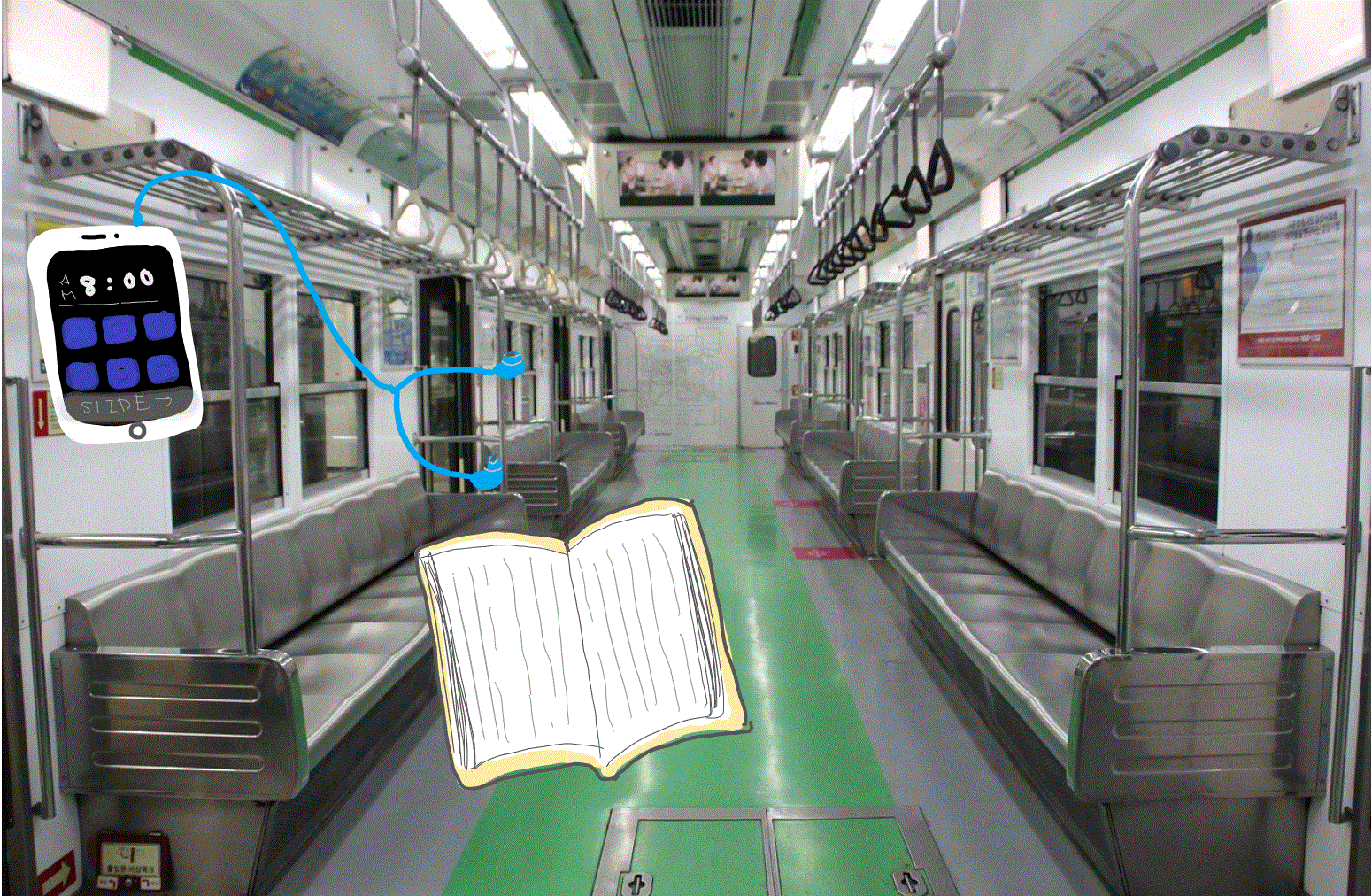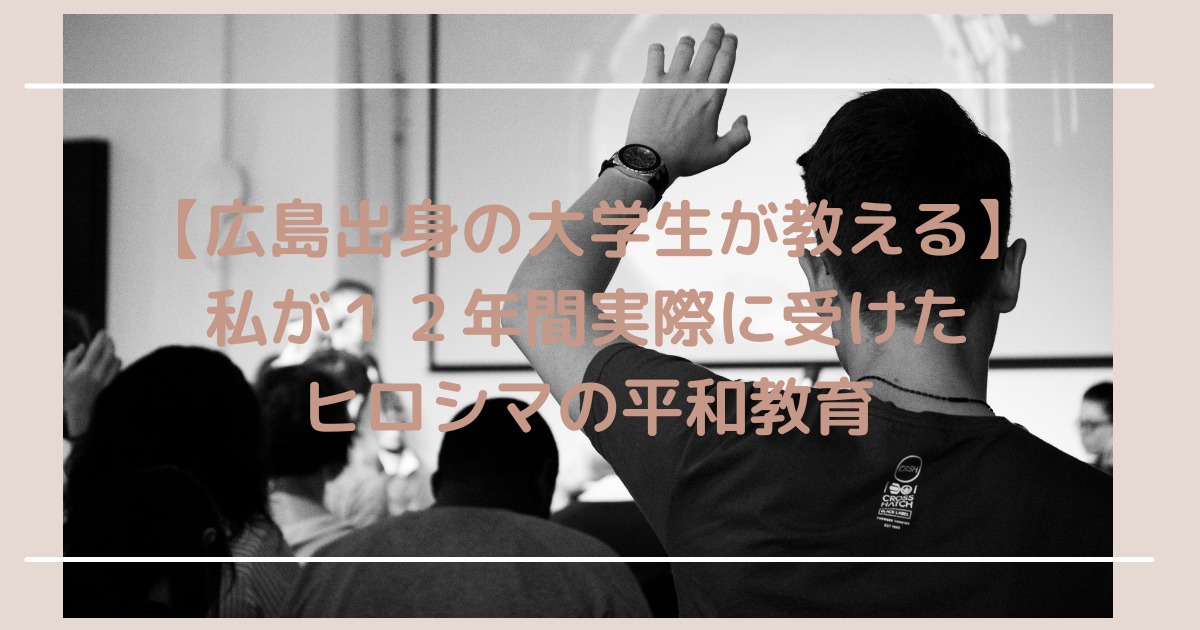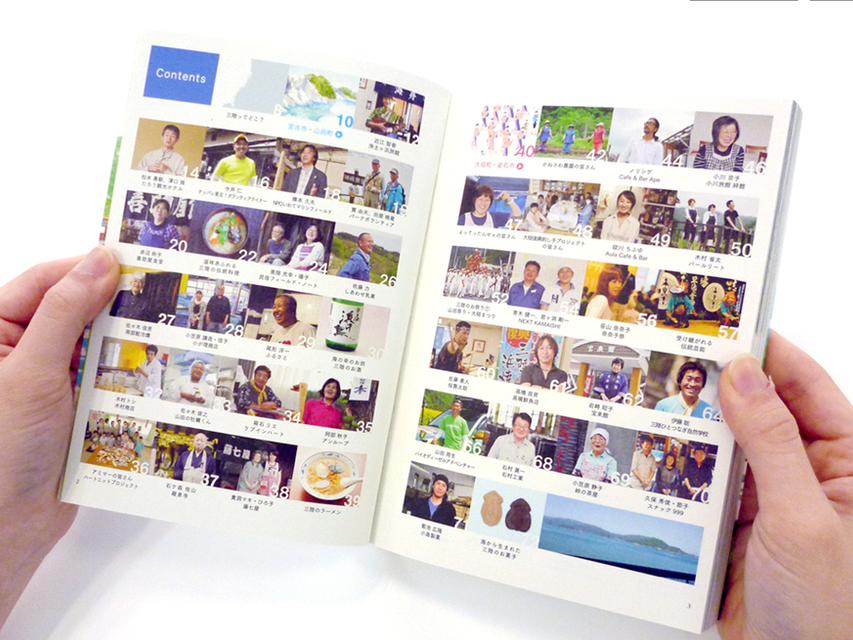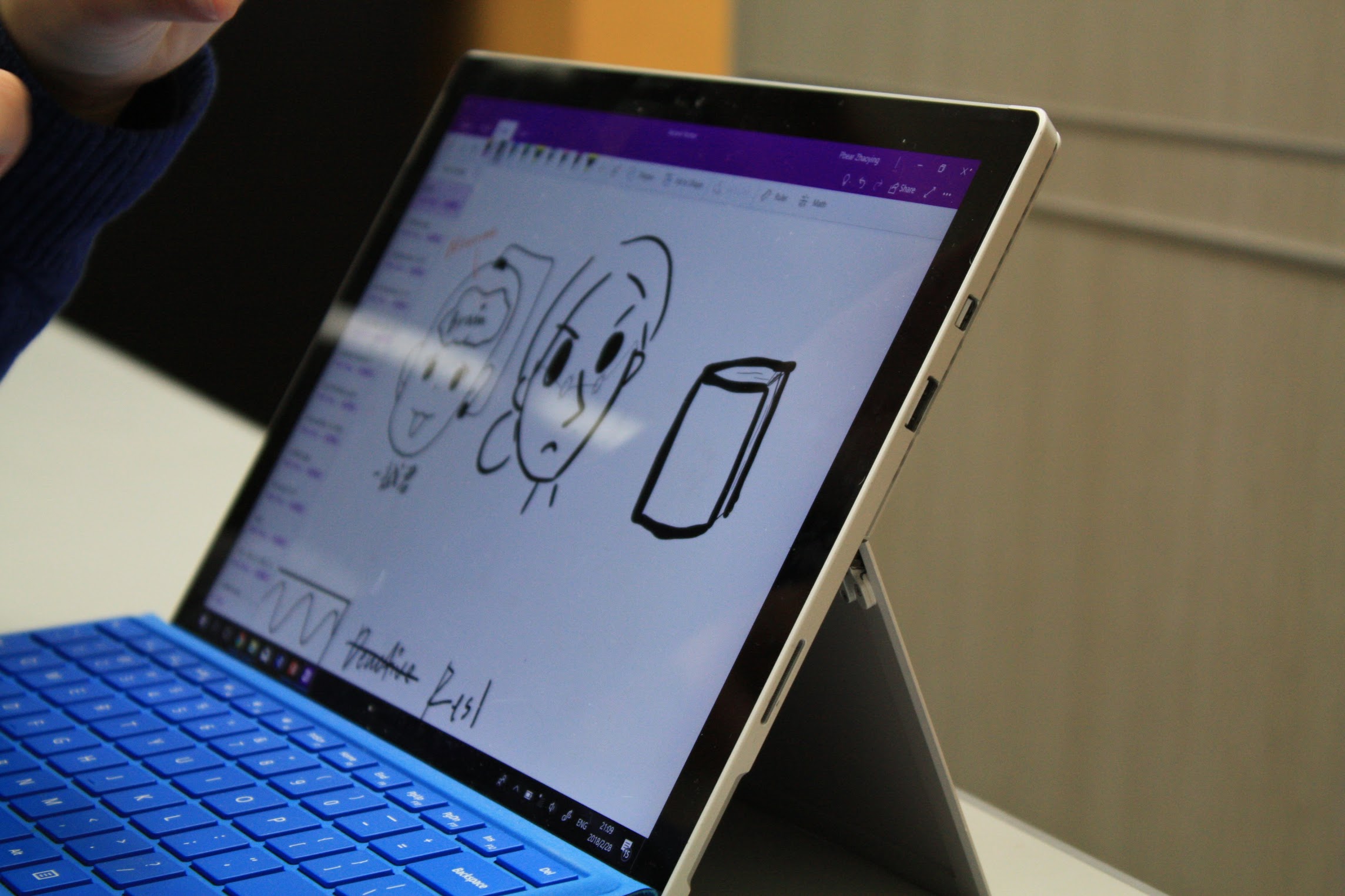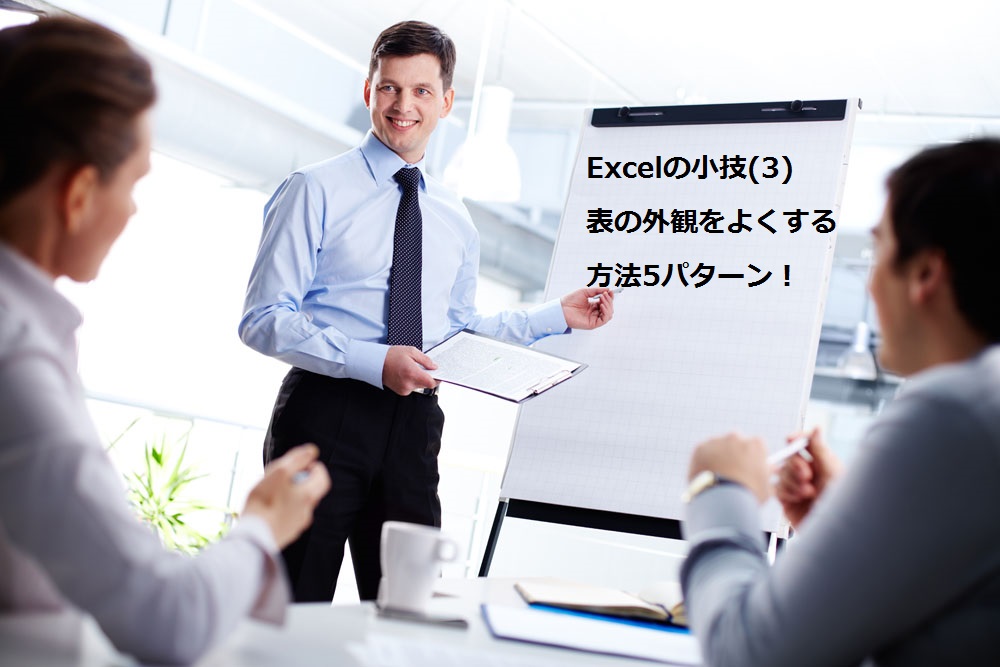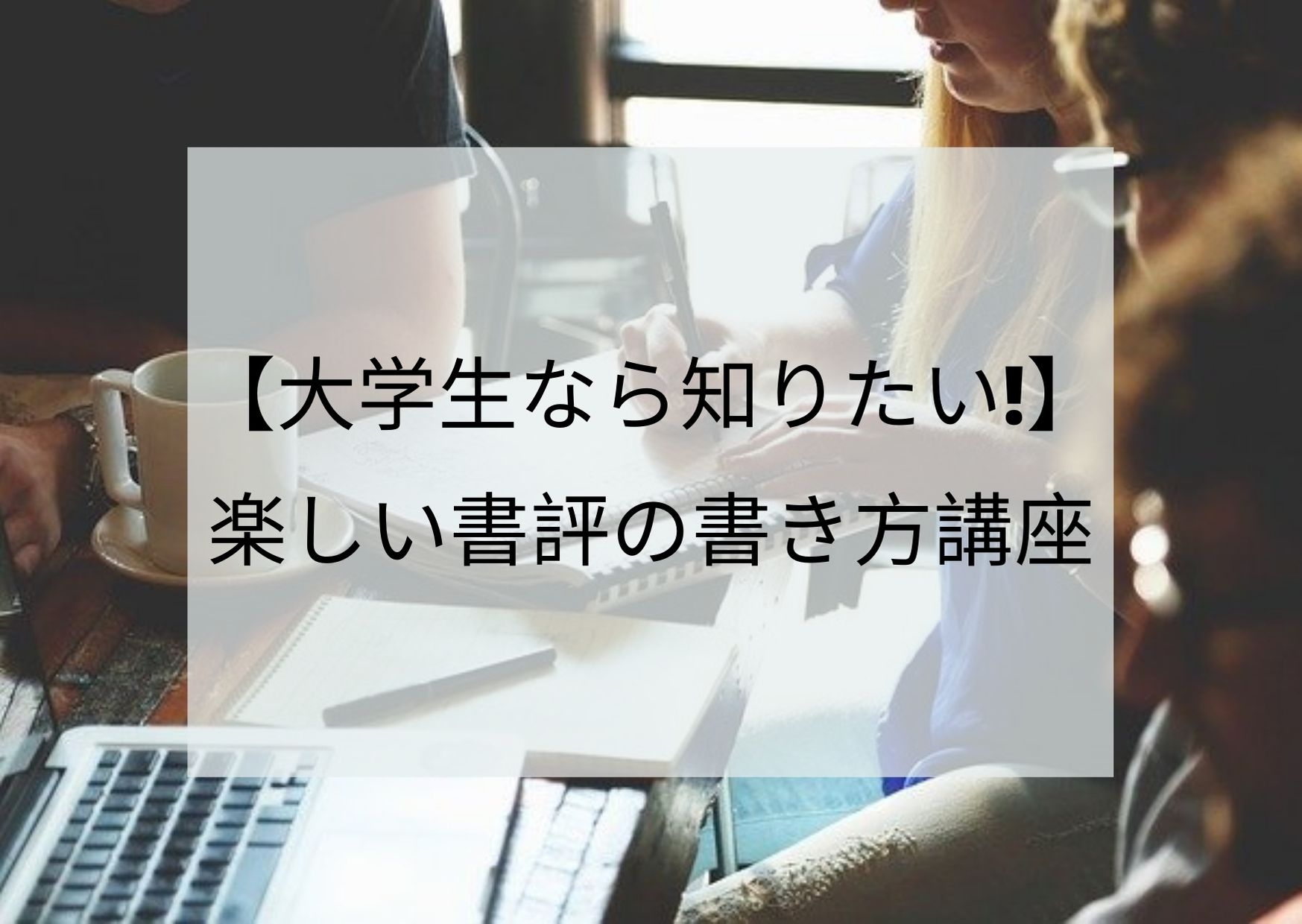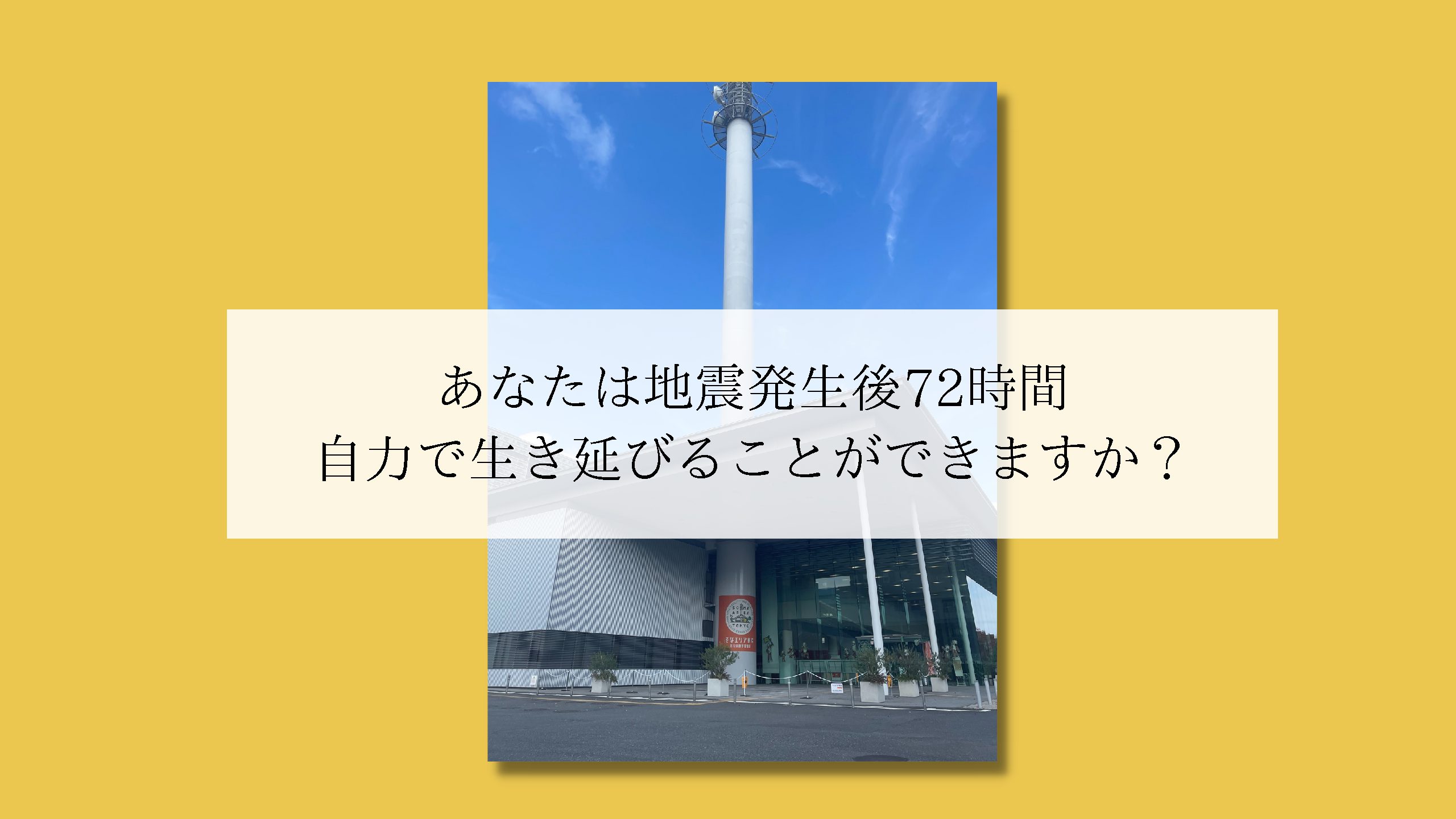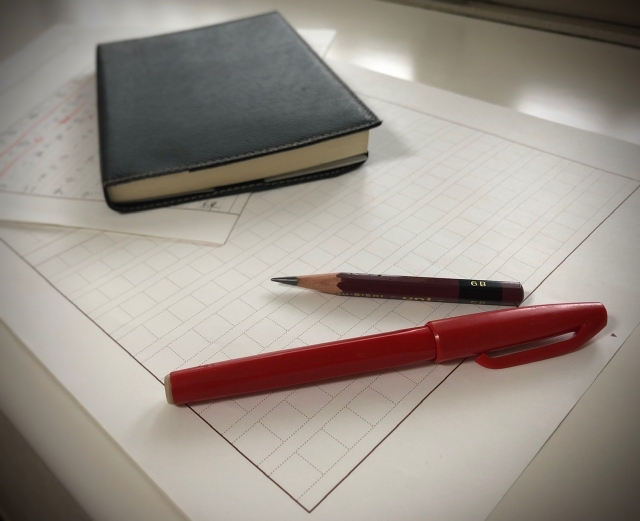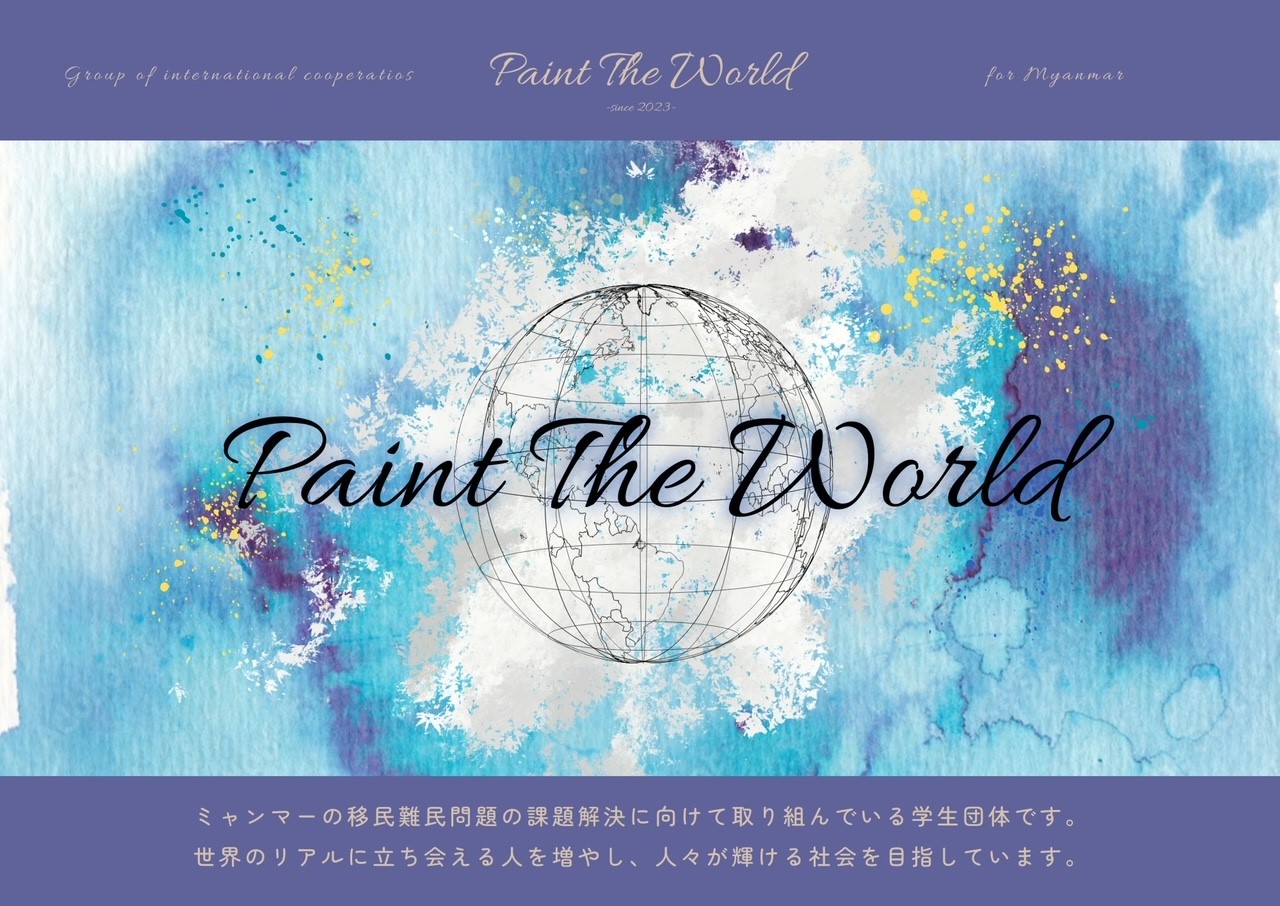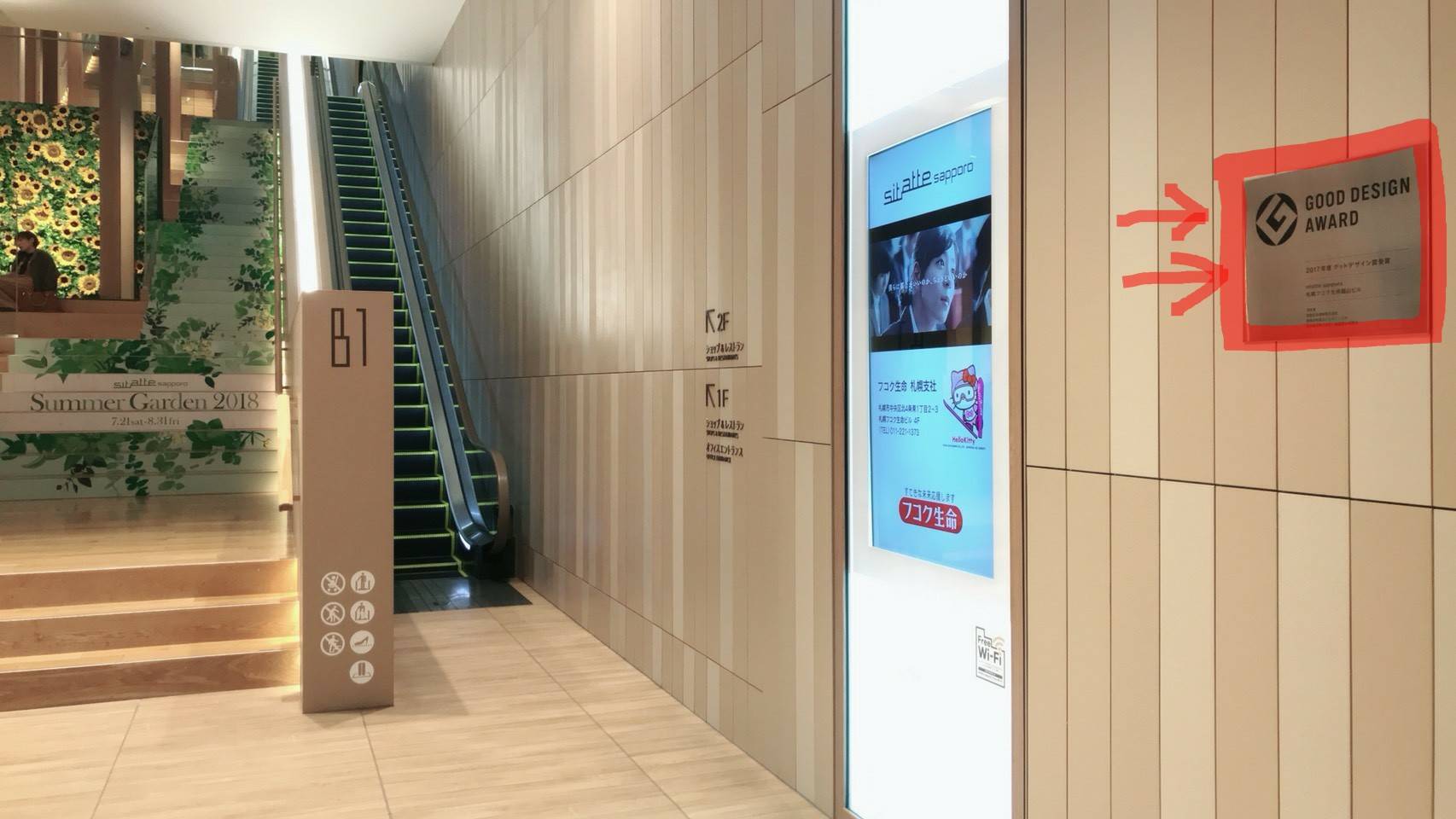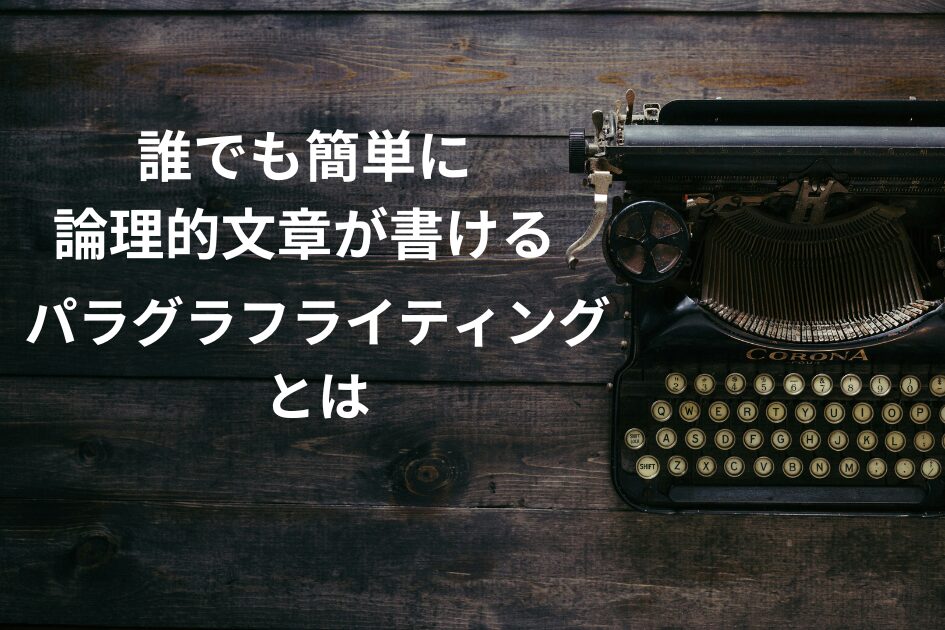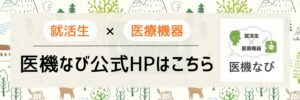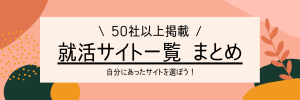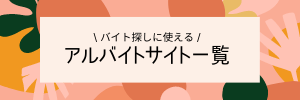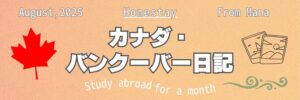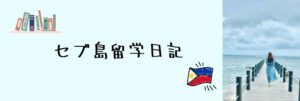勤労統計不適切調査
・「毎月勤労統計調査」とは?
厚生労働省による、雇用や賃金、労働時間の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査。調査結果は、失業手当の支給額や、国内総生産の算定にも用いられる。
毎月勤労統計調査では、厚生労働省が都道府県を通じて事業所を調べ、公表する。全国3万超の事業所に対して、従業員が5〜499人の事業所は抽出して調査、従業員500人以上の事業所は全数を調査するというルールがあった。
しかし、東京都内の500人以上の事業所約1400か所について、500カ所程度が抽出して調査されていた。従業員数の多い大企業は、中小企業と比べて賃金が高い。大企業1千社近くが調査から抜け落ちていたことにより、全国の平均賃金額が低く算出されることにつながった。
毎月勤労統計調査は、国が一部を負担する保険や助成金の決定根拠となる。実際に必要な給付額と異なり、本来の額よりも抑えられてきたといえる。修正額は数十億円になる可能性。
加えて厚生労働省は、従業員500人以上の事業所について、ほかの道府県では全数調査であったが、東京都のみ抽出調査が行われたため、東京都とほかの道府県が異なる抽出率であった。しかし、2018年1月以前の集計では、全国均一の抽出率という前提で行われていた。調査方法を変更するには総務省への申請が必要だが、その手続きが行われていなかった。
以上より今回の「勤労統計不適切調査」では、ルールと異なる調査をしていたこと、統計に影響を与える変更を公表していなかったことが問題です。
ポイントで記事を読む!
ポイント①なぜ、不適切調査が判明したのか?
総務省が厚生労働省に対して、2017年と2018年の毎月勤労統計調査における数値の不連続(あまりにも差があったこと)を指摘したためです。問題の2点目である、調査方法変更が公表されていなかったことが明らかとなりました。
ポイント②不適切調査の原因
新聞では、以下のように解説されています。
厚労省の担当者は「統計分野ではほとんどが抽出するというやり方だった。実務レベルで淡々と行われていて、統計上(賃金額などを)改竄(かいざん)するという意図はなかった」と説明。不適切調査が始まった動機や背景については今後、職員への聞き取りを進めて解明していくという。(産経新聞)
現在、公表している毎月勤労統計調査によると、物価変動の影響を除いた実質賃金は17年が0.2%のマイナスだった。厚労省の度重なる不手際は、伸び率を高くするための加工だったのではないかという疑念が広がりそうだ。(日本経済新聞)
ポイント③不適切調査による影響
今回の事態によって、統計全体の信頼を損なってしまいました。一貫性のないデータを前年同月と比較していたことについて、問題があることを認識している職員もいたといいます。
影響として、過少支給の対象者は延べ約1973万人、追加給付の総額は約537.5億円に上ります。
厚生労働省では相談窓口を設け、追加給付のための申し出を呼びかけています。対象として、育休給付なども含めた雇用保険関係、労災保険関係などがあります。
ポイント④これからの課題
財務省では、昨年12月21日に閣議決定した2019年度予算案を修正する検討に入りました。
厚生労働省は、過少給付となった人に不足分を払う方針ですがその対象者は多く、追加給付をいつ終えることができるかまったく見通せない、現住所を把握できない人も多いという問題点があります。
また、関係者の処分についても検討しています。
2019年1月12日時点での勤労統計調査についてのまとめは以上です。当記事は大学生向けに必要な情報をわかりやすくまとめたものです。数字などより詳細な情報を知りたい方は以下を参照してください。
参考
日本経済新聞(2019年1月10日夕刊、1月11日朝刊、夕刊、1月12日)
産経新聞(2019年1月12日)
時事通信社 時事ドットコムニュース(2019年1月11日)
厚生労働省ホームページ(2019年1月12日閲覧)